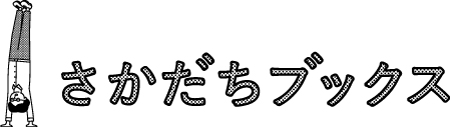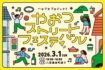【飛騨市】飛騨古川祭に行ってきました!
毎年、4月19、20日に飛騨市の気多若宮神社で行われる「飛騨古川祭」に行ってきました!年に一回、氏神の神霊が高いところにある山の神社から地域内へ降臨する神降しの日に催され、慰め和ますのが祭りの行事となっているそうです。

4月の下旬ではありますが、飛騨市はちょうど桜が見頃。さかだち編集部が到着した19日の夜は、ライトアップされた夜桜が光り輝いていました。
古川祭は国重要無形民俗文化財に指定されており、古川祭のメインともいえる「古川祭の起し太鼓・屋台行事」はユネスコ無形文化遺産にも登録されています。

こちらがその「起し太鼓」。祝い唄の唱和で幕を開け、数百人(!)のさらし姿の男性が櫓(やぐら)を担いで、飛騨古川の町並みを巡回します。「うぉーーー」という雄叫びと、「どぉぉぉん…!」と低く鳴り響く太鼓の音とともに町を駆け抜ける姿は、間近で見るとすごい熱気と迫力です!!
櫓の上で大太鼓を叩く主役 ” 太鼓打ち ” を含め、12人の男性が櫓の上に立ち、町を周ります。“ 付け太鼓 ” と呼ばれる小太鼓を大太鼓の櫓に最も近い位置につけて進むのが名誉とされているそうで、激しい先頭争いを繰り広げながら突き進んでいきます。

まちなかでは、付け太鼓をくくりつけた約3.5mの棒を垂直に立て、その上で曲芸「とんぼ」も繰り広げられます。両手を広げ、棒と共にくるくると回る姿は、まさしく、“とんぼ”のよう…!

飛騨市古川では、祭で使用する山車(だし)のことを「屋台」と呼びます。町中を曳行するだけでなく、屋台上でからくり人形や「子供歌舞伎」などの奉納芸も行われます。

子供歌舞伎は、下段が高く飛騨最古の様式を残す貴重な屋台 “ 白虎台 ” の上で子供が実際に演舞します。昭和59年の大改修の際、踊り台と源義経の人形を復元し、百十数年以上途絶えていた子供歌舞伎を復活させたそうです。
獅子舞の踊りも古川祭の見どころの一つ。連なり、お囃子(はやし)に合わせて舞う姿は圧巻で、思わず見入ってしまいます。踊りの後に獅子舞に近づくと、頭を噛まれることも…!これは獅子に噛まれることで邪気が祓われ、一年の無病息災を願うことができる縁起の良い行いといわれています。

その他にも2日間を通して見どころが満載!歴史や文化を感じつつ、飛騨らしいご飯を食べたりと、存分に古川を堪能した2日間でした。
起し太鼓が始まる際の挨拶で、“ 寒い冬が長い飛騨古川にとって、春の訪れはとても喜ばしいもの。その喜びと共になくてはならないのがこのお祭” と語らていたのが、とても心に響きました。 飛騨古川の春と貴重な文化遺産を体感することができる「飛騨古川祭」、興味がある方はぜひ、来年の春に訪れてみてくださいね!
さかだちブックスをフォローする